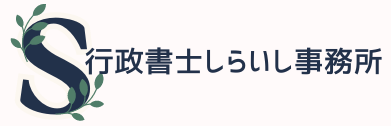酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されており、酒類小売業免許は3種類あります。
酒類小売業免許の種類
◆一般酒類小売業免許
販売場(酒屋・コンビニ・スーパー等)において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許
◆通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許
品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類のみ可能。
(取引するにはメーカーからの証明書が必要)
※酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)又は一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません。
⇒「一般酒類小売業免許」の取得が必要
※2都道府県以上にわたる場合であっても、販売場の所在する市町村(特別区を含む。)の近隣にある市町村の消費者等からの受注に基づき、当該消費者等に対し自ら配達する方法により小売を行う場合。
⇒「一般酒類小売業免許」の取得が必要
◆特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる酒類小売業免許
※自社の役員や従業員に継続的に販売(小売)する場合。
管轄行政庁
申請書提出先→販売業免許を受けようとする販売場を所轄する税務署
申請時期
申請書等はいつでも提出することができます。
審査順位は受付順。
標準処理期間
原則として、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内
登録免許税
申請には手数料は不要。
酒類の販売業免許1件につき3万円 (免許付与時に納付)
免許の有効期限
更新制度はありません 。一度取得すれば会社や事業が存続する限り有効。